2025年の宅建試験を受けたとき、正直「過去問だけじゃ足りない」と痛感しました。
覚えたつもりでも、問題の聞き方が少し変わるだけで迷ってしまう。
特に今年は個数問題が多く、文章の一字一句に神経を使う試験でした。
そんな中で気づいたのは、ただ“覚える”だけではなく、「なぜそうなるのか」まで理解して解くことの大切さでした。
- 過去問を解いても点数が安定しないと感じている方
- 過去問の“正しい使い方”を知りたい宅建受験者
- 今年の試験を受けて「何が足りなかったのか」を整理したい方
この記事でわかること
・理解して解くことで点数が安定した“過去問の使い方と考え方”
過去問の使い方で伸び悩んだ経験から学んだこと
宅建の学習では「過去問を繰り返せば合格できる」と言われます。
しかし、実際にやってみると“数をこなすだけ”では力にならないことに気づきました。
2024年末から3月までは1問1答形式で基礎固めをしていました。
テストでは選択肢の表現が変わると迷い、得点が安定しませんでした。
「知っているのに解けない」──その違和感が、勉強法を見直すきっかけになりました。
点数が伸びた“理解重視”の過去問活用法
理解型への転換点:なぜ×なのかを考える
解けなかった原因を考えるうちに、「正しい選択肢」よりも「なぜ間違いなのか」を意識するようになりました。
初めのうちは、あてずっぽうでもいいので、“この部分がこう違う” “この部分がこうなれば正しい”と
自分なりに考えて問題を解き、問題集の解説を読む。
それだけで記憶の定着率が変わり、曖昧だった知識が整理されていきました。
「あてずっぽうでも、どこが違うのか考える」
この一手間が理解の深さを変える。
4択形式で“本番力”を鍛える
6月以降は本番を意識して、4択形式の問題に切り替えました。
1問1答では知識の確認はできますが、実際の試験では似た選択肢を区別する判断力が求められます。
この形式に慣れたことで、焦らず落ち着いて選べるようになりました。
理解×反復 で得点が安定した理由
過去問を12年分繰り返す中で、出題のクセや言い回しに慣れていきました。
ただ暗記するのではなく、出題者の意図を読み取るようにすると、似た問題にも対応できるようになります。
最終的に過去問の正答率は95%近くとなり、本番でも焦らず解けました。
実践して感じた効果と次への課題
「理解して解く」勉強法を続けたことで、単なる知識の暗記ではなく、“使える知識”に変わっていきました。
ただし、試験当日は業法の問題に時間を取られ、権利関係に30分しか残らなかったのも事実です。
焦りながらも最後まで解ききり、自己採点では36点。
今は11月26日の合格発表を待っていますが、次に活かせる手応えを感じています。
\ コンテンツ準備中 /
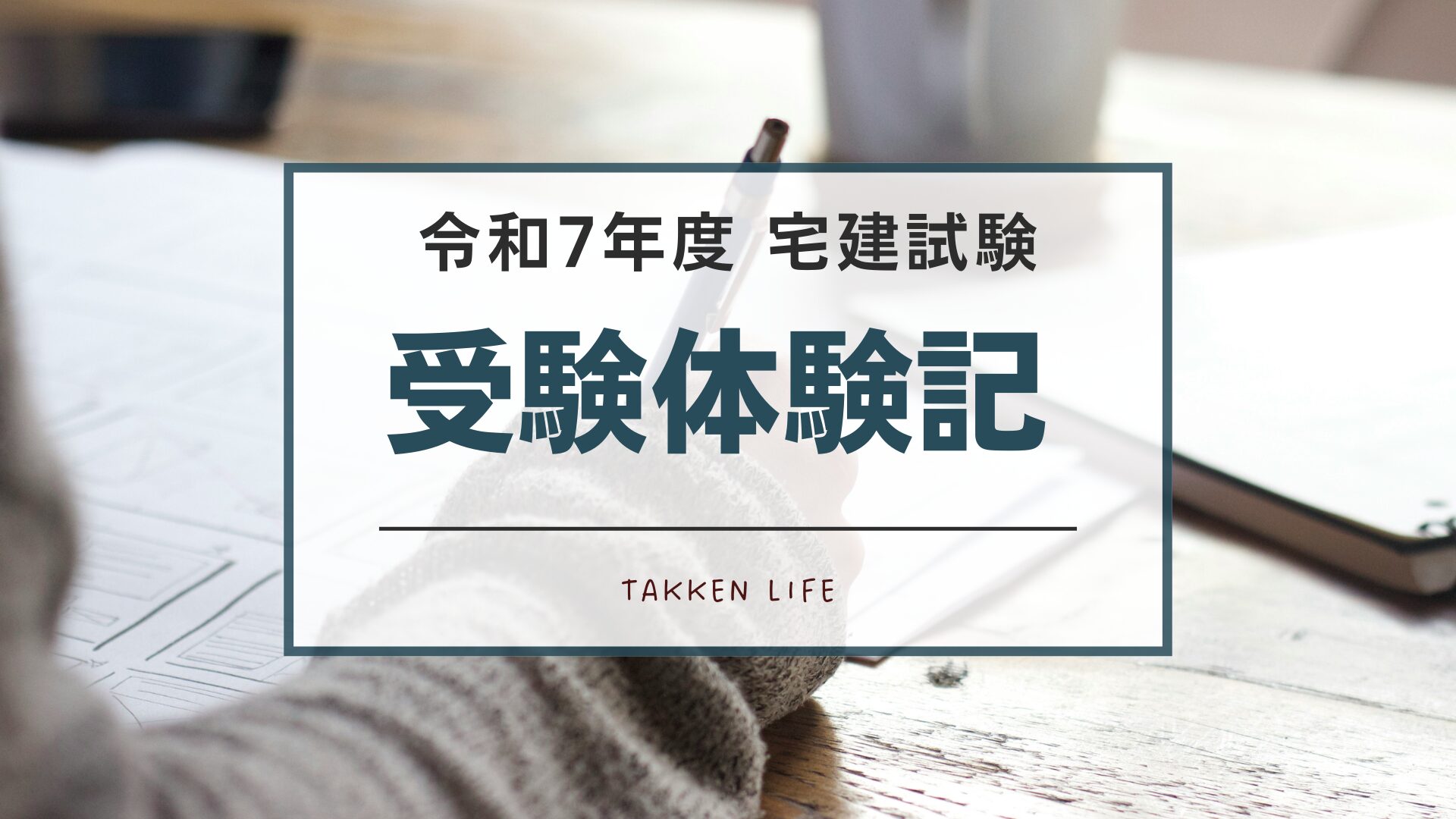
コメント