令和7年度の宅建試験は、これまでの傾向と大きく異なる印象でした。
個数問題が過去最多レベルに増え、文章も長く、慎重に読まないとミスを誘う内容。
単なる知識よりも「読みの精度」や「時間配分力」が合否を分けた年だったと思います。
- 令和7年度の宅建試験を受けた・これから受ける予定の方
- 今年の試験が難しかったと感じている方
- 勉強法を見直したい初心者〜社会人の方
この記事でわかること
・令和7年度の試験で起きた「個数問題の増加」と「時間配分の難しさ」から学ぶ、次年度の対策ポイント
今年の全体傾向(体感)
- 個数問題が過去最高クラスに増加。
- 本文が長く、設問の言い回しも慎重な読解が必要。
- とくに宅建業法は「スピードで取る」より「慎重に読む」姿勢が求められました。
宅建業法:20問中10問近くが個数問題
私は業法に時間がかかり過ぎてしまい、権利関係は残り30分という状況に。
焦ってパニックになり、問題文が頭に入らなくなりました。
感覚的には「30点も取れていないかも」と思うほど難しく感じましたが、結果は自己採点36点。
主要予備校の予想合格点も34点ラインと高く、全体的に難易度は高かったと言えます。
権利関係・法令上の制限:読みの精度がカギ
一見シンプルに見える設問でも、語尾の違いで正誤が変わる問題が多く出題されました。
「慣れ」で読んでしまうと、思い込みミスに気づけません。
過去問で培った“理解の浅い知識”が通用しなかった部分もありました。
学習法の変化と気づき(2024年〜2025年)
学習初期(2024年年末〜3月頃)は、まず問題に慣れるために1問1答形式で学習していました。
短時間で答え合わせができ、解説を読むことで少しづつ理解していきました。
6月を過ぎたあたりからは、本番形式に慣れるため4択問題を中心に解くようにしました。
ただ、実際の試験本番では「どっちだったっけ?」となる場面があり、過去問ではできていたはずの問題で迷うことも。
これは、知識を“分かったつもり”のままにしていた部分があったからだと思います。
今年の受験を通して感じたのは、1問1答形式で「正確に理解する」時間をもっと取るべきということです。
もちろん4択形式に慣れることも大事ですが、知識を「確実に」「正確に」覚える方が優先。
その後で、4択形式で実戦感覚を鍛える流れが一番効果的だと考えます。
今後の課題と改善点
- 個数問題は「正誤を積み上げる」意識で冷静に判断。
- 業法に時間をかけすぎない。全体を見て取捨選択。
- 1問1答で理解の抜けを補い、4択で本番対応力を養う。
- 焦ったときは深呼吸して「読む時間」を確保する。
焦りが出た瞬間にミスが増えるのが宅建試験の怖いところです。
「落ち着いて読む」ことが、最もシンプルで効果的な戦略かもしれません。
まとめ|“正確な理解”が合格への近道
令和7年度は、知識の丸暗記ではなく「正確な理解」が問われた試験でした。
来年以降に向けて、まずは1問1答で確実な基礎固めを。
その上で4択形式に慣れていけば、実戦でも落ち着いて対応できます。
\ コンテンツ準備中 /
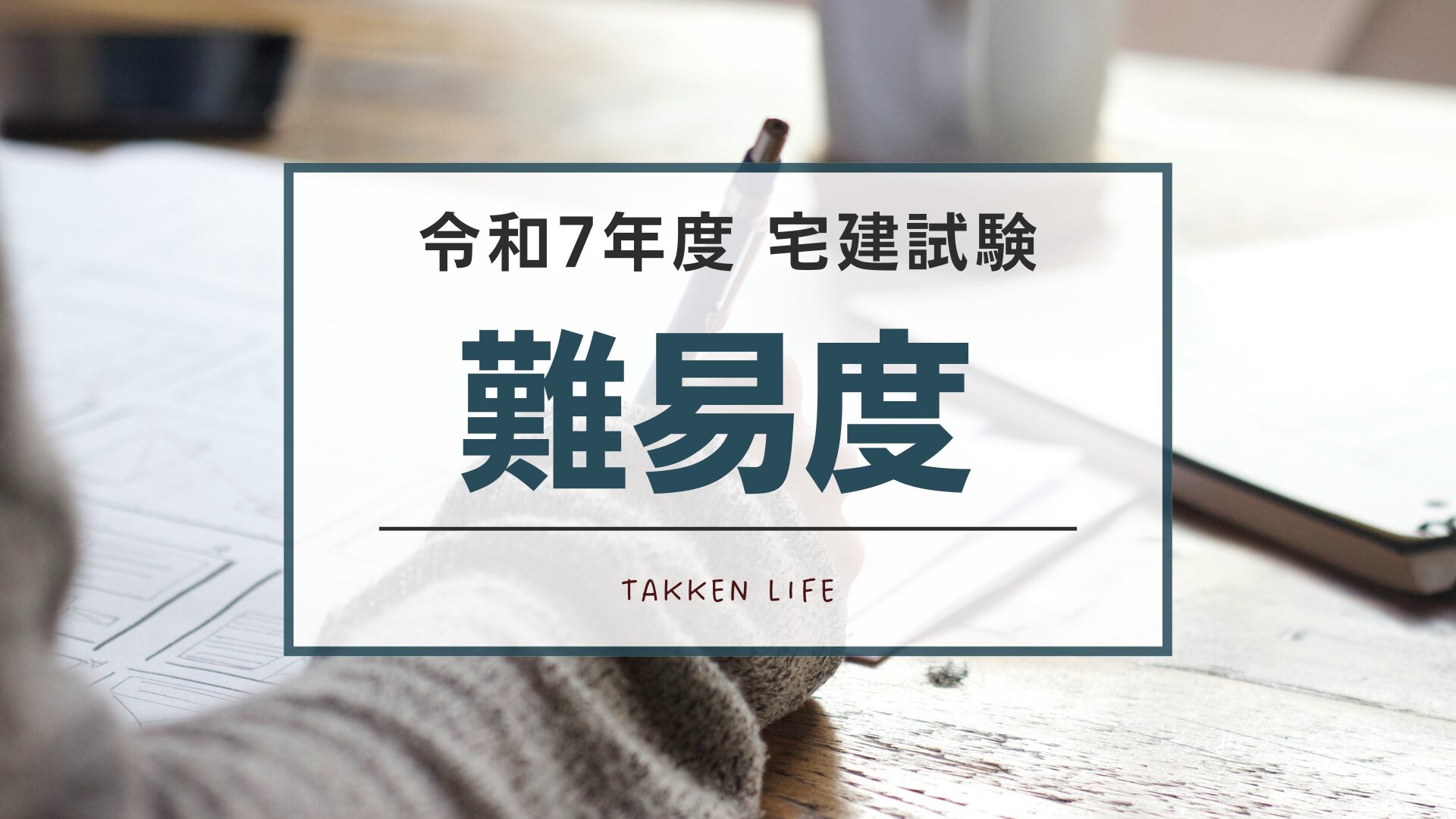
コメント