仕事と両立しながら宅建に挑戦するのは簡単ではありません。ですが、学び方を整えれば合格は狙えます。
ここでは、通学(週2回の夜間講座)で勉強した実体験をベースに、予習・復習・問題演習の進め方を紹介します。
独学の方・通信講座を使う方でも再現できるよう、できるだけ分かりやすくまとめています。
私の場合、令和4年度に独学で勉強しようと本を買い、少しだけ読んですぐに諦めました。
独学では難しかったので、ほぼ初学の状態で日建学院に通い令和7年度試験で合格ラインを超えました。
- 仕事と両立しながら宅建合格を目指している社会人の方
- 通学と独学、どちらが良いか悩んでいる方
- 効率的な宅建の勉強方法を知りたい初心者の方
この記事でわかること
・通学して気づいた「予習・復習・問題演習」の効果的な流れと、社会人でも続けられる勉強リズムの作り方
社会人でも合格できた理由(通学で実感した独学との違い)
① 通学日が決まっていて、1週間の勉強スケジュールが立てやすい
通学日は毎週 月曜・水曜の18:30〜21:00と決まってました。
授業を中心にスケジュールを組むことで、予習・復習のタイミングも明確になり、迷うことが減りました。
そのおかげで自然と習慣化でき、「この時間は勉強する」と体が覚えるようになりました。
通学には「やらざるを得ない」環境があり、それが継続の大きな力になります。
独学だと後回しにしてしまいがちな学習も、通学では自然と習慣化できました。
② ライバルの存在でやる気が続く
教室には、同じ目標を持つ仲間がいました。
「前回のテストで負けたから、次は勝ちたい」──そんな気持ちが刺激になり、勉強のモチベーションにつながります。
一人で勉強していると、気持ちが緩んだり、迷ったりすることがあります。
でも、周りに努力している人がいると「自分もやらなきゃ」と思えるんです。
大変な勉強も、同じ目標を持つ人と一緒に頑張れる環境は大きかったです。
③ テキスト+動画解説で理解が進む
テキストを読むだけだと、「何のこと?」と思うことが多いですよね。
慣れない用語だったりで理解したつもりでも、誤った認識で覚えてしまったりすることも。
そこに動画講義が加わると、図解や具体例で説明してくれるので「こういうことか!」と納得でき理解が深まります。
テキストでインプット、動画で確認。この繰り返しが、理解力を大きく伸ばしてくれました。
④ 情報交換ができる(アプリ・サイト・勉強法)
通学の良いところは、他の受講生と情報交換ができることです。
「このアプリが便利」「このサイトが分かりやすい」など、リアルな勉強法を共有できます。
自分だけでは気づけない勉強のコツを知ることで、効率が一気に上がりました。
学び方に迷ったときは、仲間の意見がヒントになることも多かったです。
こうした交流は、モチベーションを保つ上でも本当に大切だと感じました。
通信講座でも同じ流れを再現できる
今は通信講座でも、通学と同じ流れで学べます。
「予習→講義→復習→小テスト→過去問」の流れを作ることが大切です。
動画講義・小テスト・質問サポートまで揃っている講座も多く、通学とほぼ同じ環境を作れます。
まとめ|進め方が分かれば、努力は結果に変わる
通学したことで、手探りではなく「どう進めればいいか」が分かるようになりました。
独学や通信講座でも、同じサイクルを意識すれば再現できるかと思います。
焦らず、一歩ずつ積み上げていきましょう。
努力は必ず結果に変わります。
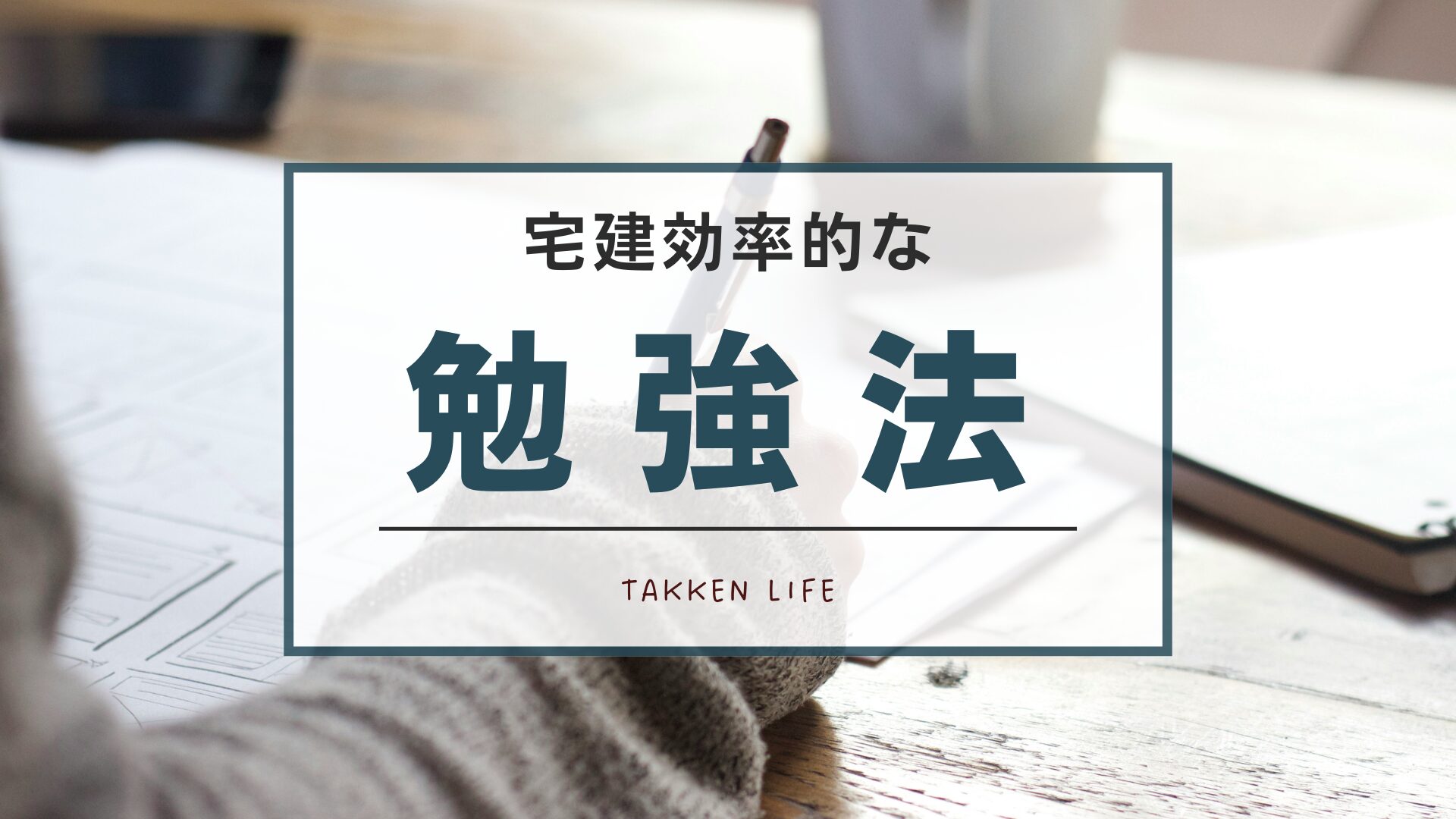
コメント