本試験が終わってから合格発表までの期間は、不安と期待が入り混じりやすい時間です。
この数週間をどう過ごすかで、結果が出た後の動きがスムーズになります。
ここでは心の整え方と、合格していた場合・していなかった場合の準備を具体的にまとめます。
- 合格発表までの過ごし方ややるべきことを整理したい人
- 結果が出た後に慌てず動けるよう事前準備をしたい人
- 不安をコントロールして勉強のリズムを崩したくない人
この記事でわかること
・合格発表までの具体的な過ごし方と、合否どちらでも迷わない事前準備
合格発表までにやるべき3つのこと
① 自己採点を整理し、根拠ベースで落ち着く
自己採点の点数と各予備校のボーダーを並べて、安心材料とリスクを言語化します。
点数の内訳を科目ごとに書き出すと、合否どちらでも次の一手にすぐ移れます。
② 合格時に必要な手続きを確認しておく
- 登録実務講習の確認(未受講なら日程の目星を付ける)
- 登録申請・宅地建物取引士証交付の必要書類チェック
- 勤務先での実務開始時期や配置の想定を共有しておく
事前にチェックリスト化しておくと、発表後に迷わず手続きに入れます。
③ 不合格だった場合の再始動プランを作る
次の勉強開始日をカレンダーに入れて、最初の1週間メニューまで決めておきます。
過去問の誤答ノートや模試の△×メモは、改善テーマ表にまとめ直します。
焦らないためのメンタル整理法
結果を気にしすぎないための「安心の根拠」を持つ
予備校のボーダーと自己採点を見比べ、感情ではなく根拠で落ち着くようにします。
SNSや他人の点数に振り回されないよう意識します。
体験談:静かに整える時間を意識する
私は自己採点が36点で、多くの予備校が34点前後をボーダー予想としていました。
発表までは「37点に上がる可能性は低い」という根拠を持って、過度に不安にならないようにしています。
趣味の映画を見たり、静かに心身を整える時間を意識しました。
焦りを消すのではなく、根拠で小さくならしていく感覚が有効だと感じました。
もし不合格でも立ち止まらないための準備
「再始動メニュー」を用意する
まずは、一問一答で基礎の確認をして、知識を思い出すところから始めましょう。
用語と基本ルールを思い出し、頭を「宅建モード」に戻します。
次に、点数が足りなかった原因を1つずつ特定します。
誤答の理由(読解ミス・語尾の見落とし・知識不足)を短くメモに残します
原因メモを潰し終えたら、4択形式に切り替えて実戦に戻していきましょう。
弱点テーマを絞る
苦手分野をすべて克服しようとすると、時間も集中力も分散してしまいます。
だからこそ、まずは「得点効率の高いテーマ」に絞ることが大切です。
たとえば
- 都市計画法(開発許可・用途地域)
- 毎年1〜2問出題。特に「開発行為の定義」「許可の要否」は定番。
- 面積要件(500㎡・1,000㎡など)は数字を押さえる。
- 建築基準法(用途制限・接道義務・容積率)
- 計算・判定問題が出やすい。条文理解よりも例題で慣れることが重要。
- 農地法・国土利用計画法(許可・届出)
- 出題頻度はやや低下傾向でも「許可の主体」と「面積要件」は鉄板。
- 似た選択肢で間違いやすいため要チェック。
- 35条・37条書面(重要事項説明・契約書)
- →毎年ほぼ必出。特に「記名押印の要否」「説明義務者(取引士)」の区別は確実に。
- 近年は電子契約・押印省略の新制度も問われています。
- 報酬額制限(媒介・代理報酬)
- 計算問題として定番。
- 「売買・貸借の上限」「片手・両手取引の違い」を整理。
- 免許制度・業者間取引・営業保証金制度
- 法令改正にも影響されやすいが、基礎ルールは安定出題。
- 「免許不要な業者」「営業保証金の供託額」など、数字系を重点的に。
この中で、過去問でミスが多かった分野から優先して潰していきましょう。
学習ログは「できるようになった項目」を書く
学習記録は、時間ではなく「できるようになった内容」を中心に書くのがおすすめです。
たとえば「都市計画法の開発許可の要否が整理できた」「35条書面の説明義務が理解できた」といった形で、1行だけでも構いません。
こうした“できたリスト”を積み重ねると、自分の成長が見えるようになります。
勉強時間の数字だけを追うよりも、理解の実感が自信に変わり、次の勉強へのモチベーションになります。
最初は小さくても大丈夫です。1日1項目、「できたこと」を書き残すだけで勉強が前向きになります。
まとめ|結果を待つ時間も学習の一部
合格発表までの期間は、心を整え、次の一歩を準備するための大切な時間です。
根拠で落ち着き、合否どちらでも迷わない準備を進めれば、発表後の動きは驚くほど軽くなります。
小さな行動を積み上げて、次のステージに備えましょう。
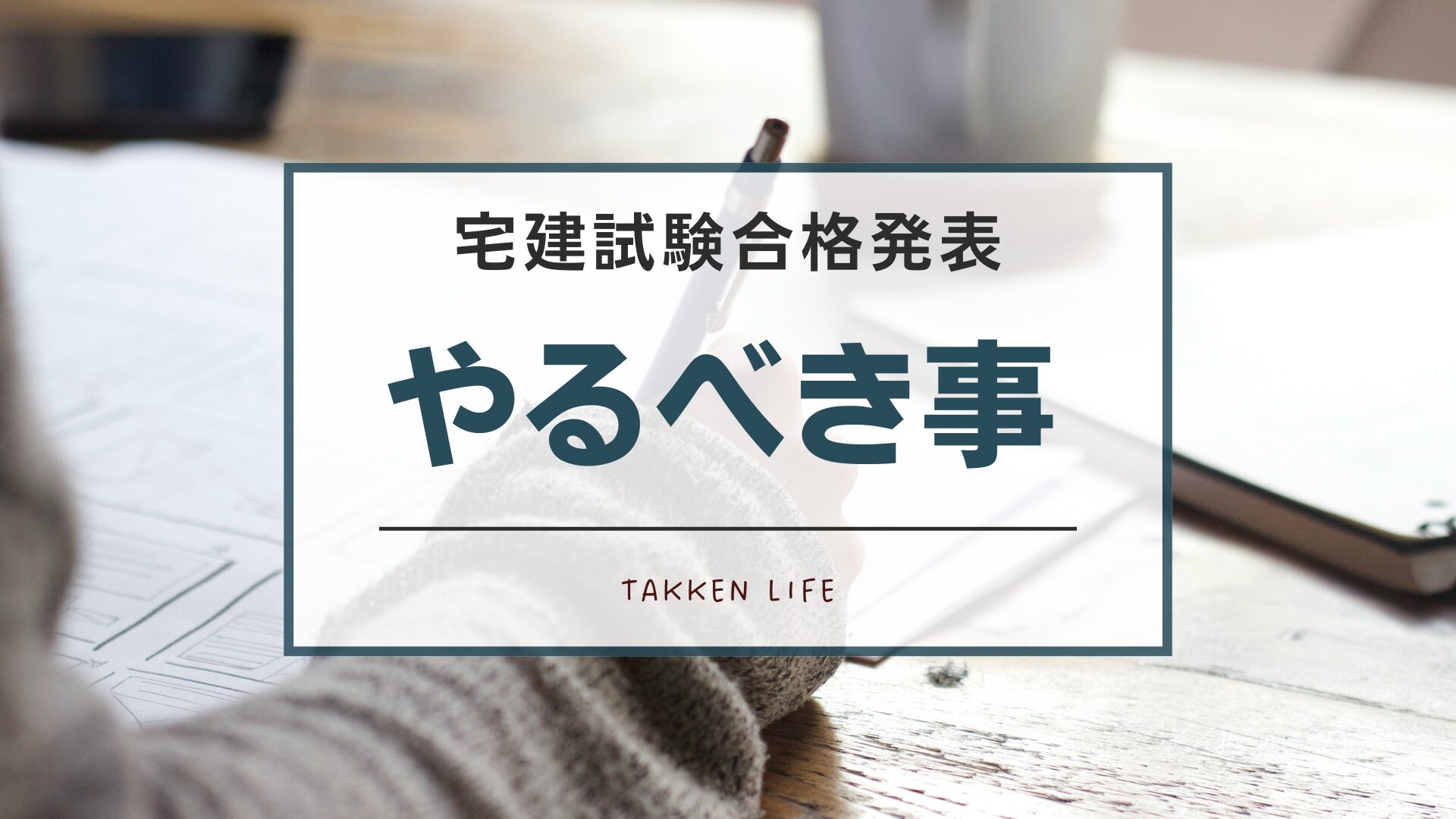
コメント